公平な判断は情熱を伴う
少し思うところがあって投稿。
言説における空間性が、一部流動的な状況に変化してから、そこに普遍的なものや公平性を見出しにくくなっているのではないかと。
twitterなどのsnsでは日々、縦軸として情報やそれ以外のことばが流れるが、それらにおける大衆迎合的なモードばかり追っていては、経験的にではあるが、幻想や風評、スティグマとしての負の連鎖のようなものに陥ってしまうことさえある。
ここで、其れに対して横軸の普遍性としてのことばの位相、つまり美を批評するための流されない判断について考える。
ドゥルーズやボードリヤールは、サイバースペースについて、コードがDNAのように配列され、それらから世界が作られるという論を立てている。
しかし例えば、後者の超現実が中心になり世界が構築されているという言説に依拠したところで、未だその外装は「自然」なのではないか。
また、専門家ではない、あるいは専門家とそのような者が混交している、あるいは遊んでいる日常空間としての共同性。そのような場所には「趣味性」がある。
カントは次のように述べている。
「趣味判断と論理的判断とは、次の点で異なっている、即ち——論理的判断は表象を概念のもとに包摂するが、これに反して趣味判断は表象をいかなる概念のもとに包摂するものでもない、ということである、もしそのようなことをしたら[趣味判断における]必然的、普遍的同意が証明によって強要されることになるからである。
それにも拘らず趣味判断は、普遍性と必然性とを要求するという点では、論理的判断に類似している、しかしそれは対象の概念に従う普遍的必然性ではなく、飽くまで主観的な普遍的必然性である〔…〕判断力は二つの表象能力即ち構想力(直観と直観における多様なものの統合とに対しては)と悟性(かかる統合の統一の表象としての概念に対しては)との合致を必要とする。〔…〕一方では表象(それによって我々に対象が与えられるところの)の合目的性に従い、また他方では自由な遊びの状態にある認識能力[構想力と悟性]の促進を目安として判断させるような感情に基づくものでなければならない、ということである。」(カント『判断力批判(上)』、岩波文庫、2013)
つまりここでカントは、趣味が論理に回収されれば個人的な趣向が担保されなくなるので、趣味判断と論理的判断を根本的には違うものとしている。
そのうえで趣味判断を主観的なものとし、多様でア・プリオリな構想力と、悟性(常識のようなもの)の同居が必要だとしている。
しかし、カントを理論的支柱としていたシラーは、ケルナーとの往復書簡である『カリアス書簡』(シラーからケルナーへ、1793年1月25日)のなかでこのように記述している。
「彼の考えは論理的なものと美的なものとを区別しようとするのには大いに役立つと思うのですが、そもそもどうも美の概念をまったく捉えそこなっているように思われます。
なぜなら、美は対象の論理的性格を克服したときに、まさにその最高の輝きを持って現れるからです。」(シラー『美学芸術論集』、冨山房、1977)また自由美と知性美とを区別したことで、アプリオリな感性に混乱を与えたとも書いている(同書、参照)。
これは主観性と合理性との峻別については符合するものの、趣味判断の内部に論理的なものを持ち込むべきではないとして対峙する。
ここでのシラーの記述は抽象的であり、カント主義的な依存もあることから、やや懐疑的に見なければならないことは確かだろうが、まさに「直観的に」書かれたこれらの文章はその本質に近いとも言える。
再びカントの言説に戻る。カントは「共通感」としての趣味判断についてこう述べている。
「しかし我々はこの《sensus communis》を、『共通(gemeinschaftlich)感覚』の理念の意味に解せねばならない、要するにかかる共通感覚は一種の判断能力——換言すれば、
その反省において他のすべての人の表象の仕方を考えの中で(ア・プリオリに)顧慮する能力なのである。〔…〕ところでこのことは、我々が自分の判断を他者の判断——と言っても、実際の判断というよりはむしろ可能的判断に引き当て、自分自身を他者の立場においてみることによってのみ可能である、またそのためには、我々自身の判断に偶然的に付着しているところの種々な制限を、考えの中で度外視する必要がある」(カント『判断力批判(上)』、岩波文庫、2013)
またそのようなものを実践するための格律としては、
(1)自分自身で考えること
(2)自分自身を他者の立場に置いて考えること
(3)常に自分自身と一致して〔自己矛盾のないように〕考えること(同書)
としている。
柄谷行人は、共通感覚は「ノーマル」を作り、それによって凡庸な作品が多く生産されるとし、さらに時代によってその感覚が移り変わり、それを突破するのは「天才」だとしたうえで、趣味性に普遍性を限定したカントに対して次のように述べる。
「では、カントは普遍性の要求を断念したのだろうか。普遍性は他の領域でみいだされるから、芸術においては共通感覚で満足すべきだというのだろうか。むろん、このような見方はまちがっている。確かに、カントは自然科学・道徳性・芸術を区別する。が、彼はそのどこにおいても、普遍性を「要求」しているのである。」(柄谷行人『トランスクリティーク』、岩波現代文庫、2013)
この後、自然科学との接続を行うために、柄谷はクーンのパラダイム理論と共通感覚を接合させる。これはある意味、時代の輪としてのエピステーメーを作り出すようなものに近い。
吉本隆明は、ヘーゲルの『美学』を持ち出し、このように述べる。
「〔…〕芸術の内容も形式も、表現させられた芸術(作品)そのもののなかにしか存在しないし設定されない。そして、これを表現したものは、じっさいの人間だ。それは、さまざまな生活と、内的形成を持って、ひとつの時代のひとつの社会の土台の中にいる。その意味では、もちろんこのあいだに、橋をかけることが出来る。この橋こそは不可視の〈かささぎのわたせる橋〉(自己表出)であり、芸術の起源につながっている特質だというべきだ。」(吉本隆明『言語にとって美とはなにかⅡ』、角川ソフィア文庫、2001)
ここでの内容と形式というのはヘーゲルの用語であり、初めに内容が浮かび、その後形式の方へと欲望が移行する。主観と客観の対立が個人の内的なものへ向かうことは、趣味性における主観を考察するカントと類似点がある。
批評における主観とその「尺度」については小林秀雄が『様々なる意匠』においてこう語る。
「「自分の嗜好に従って人を評するのは容易な事だ」と、人は言う。然し、尺度に従って人を評することも等しく苦もない業である。常に生き生きとした嗜好を有し、常に溌剌たる尺度を持つという事だけが容易ではないのである。人々は人の嗜好というものと尺度というものとを別々に考えてみる、が、別々に考えてみるだけだ、精神と肉体とを別々に考えてみる様に。例えば月の世界に住むことは人間の空想となることは出来るが、人間の欲望となる事は出来ない。守銭奴は金を貯める、だから彼は金を欲しがるのである。」(小林秀雄『Xへの手紙・私小説論』
、新潮文庫、2013)
また、上記のような他者性としての尺度から逸脱した、あるいは印象批評というクリシェを回避するための批評精神を、小林はボードレールに見出す。
「兎も角私には印象批評というという文学史家の一熟語が何を語るか全く明瞭でないが、次の事実は大変明瞭だ。所謂印象批評のお手本、例えばボオドレエルの文芸批評を前にして、船が波に救われる様に、繊鋭な解析と溌剌たる感受性の運動に、私が浚われて了うという事である。」(同書)
最後に、ボードレールの「群衆」を引用する。
「群衆と孤独。活動的で多産な詩人にとって、これらは相等しく、相互に交換可能な二つの言葉だ。自己の孤独のなかに群衆を住まわせることのできない者が、あわただしい群衆の中にあって一人でいられるはずもない。」(『ボードレール——パリの憂鬱』、みすず書房、2006)
様々なパースペクティブにおいて、「私」から「他者」を見つめること、書くこと、遊ぶこと、批評することは結局、自己の内面における感情の発露としてのことばとなり立ち現われるそれらを書き留め、生の痕跡として残すことなのかもしれない。内面が豊かであればあるほど、ひとのことばを上手く受け入れることや、他方、深い沈想へと自己を導く事もできる。そんな世界に、本物の他者が現れることをいつも願っている。

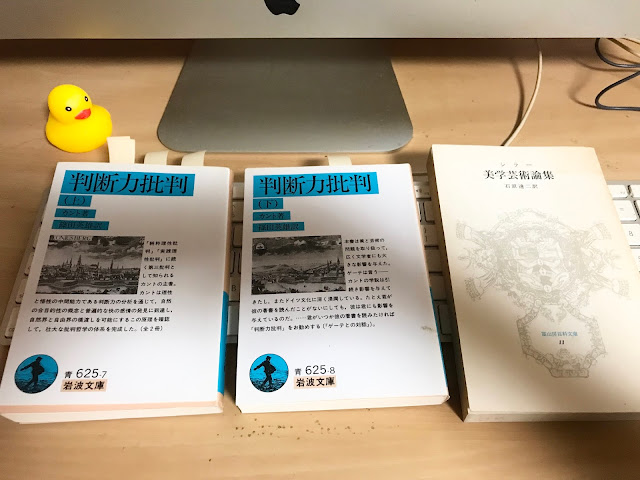
コメント
コメントを投稿