とあるエンブレムについて
オリンピックのエンブレム、ロゴマーク、ロゴタイプについて、少し落ち着いて考えてみたい。というのも、やはり国家レベルのスポーツイベントということもあり、イデオロギーや煽動に満ちた――スポーツにそのような考え方が持ち込まれる事自体がそもそも疑問ではあるのだが――言説が数多く見受けられるからである。しかしそれは本来、出稿費用などの金額の問題以前に、意匠の完成度の視点から語られるべきものであり、どなたか冷静な批評言説を書いている方はいないものかと思い探してはみるものの、なかなか見つからないし、過去のオリンピックのロゴをまとめたり、終始、似ているロゴを比較したりする記事ばかりである。そしてこれは、広告会社や仲間内におけるパワーゲームのようなものではなく、むしろそれらの「全体性」をある意味では脱構築的に冷静に批評する必要性を感じている。
個人的には、前回の佐野氏のデザインに対しては批判的な態度を貫いている。
その理由は、盗用なのではないかという――そもそも消費社会は記号の差異のネットワークで構築されるという考え方もあり、すべてのデザインが網の目状に近接している――懐疑の視点では全く無く、「前時代的」という意味において批判的である。デザインにおける「モードの循環」が遅いのだ。だから、それが取り下げられたことに対しては、世界の注目が集まるデザインとして、及びその情報の流通などを考えれば、結果としてよかったのではないかと考えている。
一方、佐野氏のデザインした制作物は、基本的に非言語的なコミュニケーションという面ではむしろ好印象を持っている。しかし、「何が前時代的だったのか」ということに関しては、歴史を遡れば自ずと浮き彫りになる。ただ、尋問のように調べ上げるようなことには興味が無い。少しでもデザインに対する思考が良い方向へ変化していけばいいと考えている。
彼が制作にあたり影響されたという亀倉雄策は、1964年の東京オリンピックにおけるロゴマーク、ロゴタイプなどのアート・ディレクションを行ったことはもはや言うまでもない。それは経済成長真っ只中で、大量生産・大量消費に裏付けられた人々の価値観の壮大なビジョンとして描かれたオリンピックというストーリーの最中でのこと。そのような、大きなうねりのような時代の雰囲気と、亀倉の思想が共鳴したのである。
上に掲載したポスターは、亀倉がライフワークとして取り組んだデザイン誌『クリエイション』Vol.21からの出典。今はもはやデッドストックとなっているが、どこか専門的なライブラリーに行けば読むことが出来るだろう。
彼のデザインの特徴は、「幾何学的表現」を平面的に大胆にレイアウトすることで、視覚的なインパクトと視認性を獲得するというもの。このようなシンプルさ・ミニマルさが大会を彩り、後に反響を呼ぶこととなる。
柏木博は、以下のように語っている。
「〔…〕東京オリンピックでは、視覚的なデザインが決定的な力を持つはずであるという予見のもとに、当時、最大の規模のデザイン計画が実施された。公式プログラム、各競技のマーク、ポスターなど膨大な数の要素の全体計画が必要であった。例えば、欧文文字のタイプフェイスひとつまでも決定しなければならなかった。タイプフェイスは、結局、当時揃えられるサンセリフ体は、日本ではニュースゴシックしかなかったので、そうした条件の中からニュースゴシックが選択されることになった。」(『クリエイション』Vol.21より)
また、同誌に拠れば、デザインチームには評論家の勝見勝、デザイナーの原弘がいた。亀倉は主にポスターを担当している。また、タイプフェイスにおけるサン・セリフ体は機能合理主義的な側面があり、当時の消費社会の状況を表していると言って良いだろう。
このような、幾何学模様とシンプルなレイアウトは、勿論他の制作物にも見られる。
これらのニコンのポスター(『クリエイション』Vol.21より出典)は、亀倉のアイデンティティが詰まったものとされている。
木島俊介はこの制作物について同誌上でこのように述べている。
「〔…〕色は、それが塗られる面がひろくなればなるだけ力を得て目立つこととなる。ポスターのごとく、一瞬のうちに見る人の視線を引かなくてはならない作品の制作にあたっては、この鉄則は重要である。例えば、亀倉が好んでいたカッサンドルのポスターの魅力は、描写対象を思い切ってクローズアップするところから生ずる、当時としては圧倒的な色面効果であり、それによって一世を風靡することとなるのだが、単なる色面の配列だけでは、画面は平面的で単調になる。カッサンドルはそれを極端に増長された西欧伝統の遠近法と明暗の対比によって救っているのであったし、亀倉が大いに研究したと語り、やがて親しく交際することとなったハーバート・バイヤーやマックス・フーバーなどバウハウス系のデザイナーたちの仕事もおおむねこの方法を基本としているのである。」(『クリエイション』Vol.21より)
上記のニコンのポスターについては立体的な陰影が無いが、レイアウトのバランスについてはダイナミックさがあり、またその後に制作したオリンピックのポスターを見れば、写真の立体性における奥行きとグラフィックの平面性の同居が、そこへ結実していることが解るだろう。
ひとびとは現実とパラレルしたネット上のデータベースを駆使し、画像をGoogle画像検索などにかけていたが――個人的にはこのカリフォルニア・イデオロギー的な装置に批判的だが――このようなことは本来作り手の内面から生み出される意匠を侮辱しているような行為に思えてならない。人に寄り添うべきデザインというものは、そのようなものを民主的などと言わないし、本来「他者への解決策を提示するもの」だろう。しかし、それがある意味ではコードにおいて作られた世界の「モデル」(J.B)なのだとしたら、このような世界に上手く適応しなければ、デザイナーもサヴァイヴ出来ない時代ということなのだろうか。
個人的には、前回の佐野氏のデザインに対しては批判的な態度を貫いている。
その理由は、盗用なのではないかという――そもそも消費社会は記号の差異のネットワークで構築されるという考え方もあり、すべてのデザインが網の目状に近接している――懐疑の視点では全く無く、「前時代的」という意味において批判的である。デザインにおける「モードの循環」が遅いのだ。だから、それが取り下げられたことに対しては、世界の注目が集まるデザインとして、及びその情報の流通などを考えれば、結果としてよかったのではないかと考えている。
一方、佐野氏のデザインした制作物は、基本的に非言語的なコミュニケーションという面ではむしろ好印象を持っている。しかし、「何が前時代的だったのか」ということに関しては、歴史を遡れば自ずと浮き彫りになる。ただ、尋問のように調べ上げるようなことには興味が無い。少しでもデザインに対する思考が良い方向へ変化していけばいいと考えている。
彼が制作にあたり影響されたという亀倉雄策は、1964年の東京オリンピックにおけるロゴマーク、ロゴタイプなどのアート・ディレクションを行ったことはもはや言うまでもない。それは経済成長真っ只中で、大量生産・大量消費に裏付けられた人々の価値観の壮大なビジョンとして描かれたオリンピックというストーリーの最中でのこと。そのような、大きなうねりのような時代の雰囲気と、亀倉の思想が共鳴したのである。
《Poster for '64 Tokyo Olympics 東京オリンピックのポスター》1962
Art Direction: Yusaku Kamekura, Photo: Jo Murakoshi, Osamu Hayasaki
《Poster for '64 Tokyo Olympics 東京オリンピックのポスター》1963
Art Direction: Yusaku Kamekura, Photo: Jo Murakoshi, Osamu Hayasaki
《Poster for '64 Tokyo Olympics 東京オリンピックのポスター》1961
Art Direction: Yusaku Kamekura
上に掲載したポスターは、亀倉がライフワークとして取り組んだデザイン誌『クリエイション』Vol.21からの出典。今はもはやデッドストックとなっているが、どこか専門的なライブラリーに行けば読むことが出来るだろう。
彼のデザインの特徴は、「幾何学的表現」を平面的に大胆にレイアウトすることで、視覚的なインパクトと視認性を獲得するというもの。このようなシンプルさ・ミニマルさが大会を彩り、後に反響を呼ぶこととなる。
柏木博は、以下のように語っている。
「〔…〕東京オリンピックでは、視覚的なデザインが決定的な力を持つはずであるという予見のもとに、当時、最大の規模のデザイン計画が実施された。公式プログラム、各競技のマーク、ポスターなど膨大な数の要素の全体計画が必要であった。例えば、欧文文字のタイプフェイスひとつまでも決定しなければならなかった。タイプフェイスは、結局、当時揃えられるサンセリフ体は、日本ではニュースゴシックしかなかったので、そうした条件の中からニュースゴシックが選択されることになった。」(『クリエイション』Vol.21より)
また、同誌に拠れば、デザインチームには評論家の勝見勝、デザイナーの原弘がいた。亀倉は主にポスターを担当している。また、タイプフェイスにおけるサン・セリフ体は機能合理主義的な側面があり、当時の消費社会の状況を表していると言って良いだろう。
このような、幾何学模様とシンプルなレイアウトは、勿論他の制作物にも見られる。
《Poster for camera lenses カメラレンズのポスター》、1955
《Poster for Nikon ニコンのポスター》、1955
木島俊介はこの制作物について同誌上でこのように述べている。
「〔…〕色は、それが塗られる面がひろくなればなるだけ力を得て目立つこととなる。ポスターのごとく、一瞬のうちに見る人の視線を引かなくてはならない作品の制作にあたっては、この鉄則は重要である。例えば、亀倉が好んでいたカッサンドルのポスターの魅力は、描写対象を思い切ってクローズアップするところから生ずる、当時としては圧倒的な色面効果であり、それによって一世を風靡することとなるのだが、単なる色面の配列だけでは、画面は平面的で単調になる。カッサンドルはそれを極端に増長された西欧伝統の遠近法と明暗の対比によって救っているのであったし、亀倉が大いに研究したと語り、やがて親しく交際することとなったハーバート・バイヤーやマックス・フーバーなどバウハウス系のデザイナーたちの仕事もおおむねこの方法を基本としているのである。」(『クリエイション』Vol.21より)
上記のニコンのポスターについては立体的な陰影が無いが、レイアウトのバランスについてはダイナミックさがあり、またその後に制作したオリンピックのポスターを見れば、写真の立体性における奥行きとグラフィックの平面性の同居が、そこへ結実していることが解るだろう。
カッサンドル《ノルマンディ》
マックス・フーバー《BRARNDLI/fantasie》
ハーバート・バイヤー《ユニバーサル・アルファベット》
※サン・セリフ体ではありません
亀倉が少年時代に読んでいたstaatliches bauhaus in weimar
亀倉がバウハウスに影響を受けたことはよく知られている。つまり、バウハウス的、あるいはアール・デコにおけるシンプルさというのは、ある側面においては当時の社会の「機械的な生産様式」に密接に結びついたデザインなのである。
モノや商品に依拠した時代、そのようにシンプル化されたグラフィックや家具、建築などは、一方で形式的思考に陥り、単純化されている。つまり、バウハウスに影響された亀倉雄策のような抽象的で平面的な表現を現代に応用すれば、そこに必ず矛盾が生じてくる。
どういうことかというと、モダンデザインは「モノや商品」に根ざしていたが、ポストモダン以降の世界は、「モノや商品」と「デザイン(記号)」の遊離(ジャン・ボードリヤール、以後J.B)が起きたのだから、過去の生産中心の時代とは全く違ったデザインが本来必要とされるのである。
しかし、記号の差異だけが消費されるという意味では、今後、モノの物質性が失われていくのではないかという危機感を抱いている。
また、ネット上のサイバーカスケードや、イデオロギー対立などを見ていると、大きな物語がまだ大きな物語として機能していた時代のような全体性やそれにより作り出される大衆が、批判を浴びせたりしていて胸が痛かった。そのようなものは、現代では本来、多様な方向へと開かれている。
しかし、記号の差異だけが消費されるという意味では、今後、モノの物質性が失われていくのではないかという危機感を抱いている。
また、ネット上のサイバーカスケードや、イデオロギー対立などを見ていると、大きな物語がまだ大きな物語として機能していた時代のような全体性やそれにより作り出される大衆が、批判を浴びせたりしていて胸が痛かった。そのようなものは、現代では本来、多様な方向へと開かれている。
ひとびとは現実とパラレルしたネット上のデータベースを駆使し、画像をGoogle画像検索などにかけていたが――個人的にはこのカリフォルニア・イデオロギー的な装置に批判的だが――このようなことは本来作り手の内面から生み出される意匠を侮辱しているような行為に思えてならない。人に寄り添うべきデザインというものは、そのようなものを民主的などと言わないし、本来「他者への解決策を提示するもの」だろう。しかし、それがある意味ではコードにおいて作られた世界の「モデル」(J.B)なのだとしたら、このような世界に上手く適応しなければ、デザイナーもサヴァイヴ出来ない時代ということなのだろうか。
更にデリダ的に言えば、「決定」は、決定を下す主体だけによるものではないのである。つまり、これが本来の(民主的といわれているような)判断なのではないか。その点、新たに公募されたデザインを、専門家以外の外部有識者をも呼んで審査するというプロセスに関しては割と好印象(制作物のクオリティが上がるかどうかは若干の疑問)で、少しは風通しが良くなると思う。
オリンピックは今日日、国を動かすような一大イベントではないし、高度経済成長期のような高視聴率も狙えない。そのような中、デザインという側面においても、どのようにそれらが設計されていくのか注意深く見守っていかねばならないと感じる。
サン・セリフ体に関する参照: (typetuto.jp)
《BRARNDLI/fantasie》(news.mynavi.jp)
《ノルマンディ》(albatro.jp)
《ユニバーサル・アルファベット》(blog.justanotherfoundry.com)
staatliches bauhaus in weimar: (metmuseum.org)










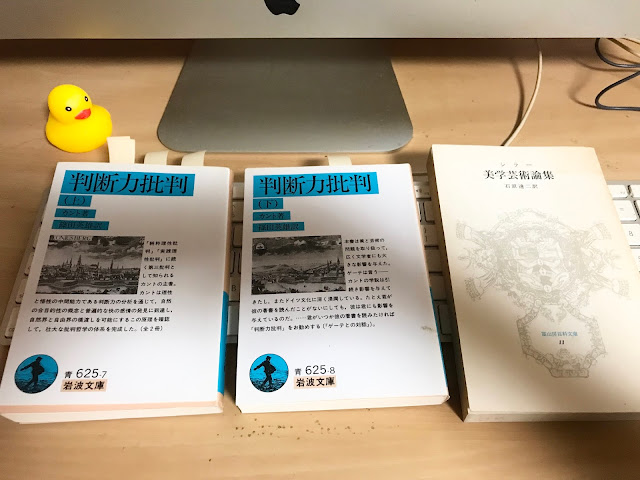
コメント
コメントを投稿