されど、ひとは間違える。――追悼:ウンベルト・エーコ
先日、作家・ウンベルト・エーコが亡くなった。読者の一人として哀悼の念を表したい。
彼は、『薔薇の名前』や、私が持っている著作では、その後に出版される『フーコーの振り子』という長編小説でその名が知られているが、個人的には記号学者としての彼のほうに馴染みが深く、ソシュールや、チョムスキーを凌駕するほどの、その研究量における圧倒的な情熱において、私は虜にされたのであった。
その理由は列挙すればいとまがないが、記号学として、いち早くプログラム言語に焦点を当てているからというのがそのひとつ。以前とある論文で、彼の二進法的世界に於ける言語活動の探求過程について論じたこともある。
私はデザイナーだったので、プログラミングはほとんどやらないし、基本的なHTMLの語彙しか持ち合わせていないのだが、それらのコードの羅列が社会変革を起こし続けていることはまぎれもない事実であり、そしてそうなるであろうと未来を見通していた(先日の報道でもあったように、イタリア政府の見解には、「未来を予測した」という旨があり、これは「美学における天才性」としての敬意であろう)彼には、やはり先見の明があった。
ライプニッツから着想した彼のコードにおける思想は、それらの序列が天文学的な領野にまで到達するようなスケールであった。
彼は、著書『完全言語の探求』の中で、コードの序列は複雑で人工的な記号系を形成するが、知らない単語や推論におけるエラーなどが、コードとしての文章により算出され、補完されることによりそれらの穴埋めが出来るのではないかということを述べており、それをライプニッツに見ている。これが、いわゆる「盲目の思考」の一端である。数学的論理学としてのそれは、言葉に規定された内容から切り離された、意味論的ではない、「印」としての操作のルールを作成すれば、未知の世界へ我々を誘うというものである。
逆説的に言えば、基本的に人工言語は命令された文章(コード)にエラーを起こさないが、人間の文章にはエラーが起き、だからこそ人間なのだ、ということも出来る。これは特に自己防衛として書いているわけではないが、しょっちゅう間違いを起こす私のような人間でも、完全に機械から身体や脳を支配されたわけではないということを、認識できるのである。
一方、意味論としての記号論は、無限に増幅され、人間の認識不可能な次元に突入するため、自然言語の代行を完全に行うことは出来ない。自然言語は「経験的なこと」、つまり時間性と空間性に基づき成立しているとエーコ自身が言うように、人間の言語の統制の限界でありそれらの総体としての概念を構築できない。これが、ライプニッツの限界なのであった。
しかし、エーコはそれらの副産物として、「個別的なもののカタログ化」という言葉を使い、それらの数学的に構築された情報の網の目により、「像」(現代で言うビッグデータ)が浮かび上がるとしている。
以前診断されたように、反復強迫だからなのか、ストレスからなのか、よく誤変換が起きる。しかし、現在は、GoogleIMEのような、ブラウジングや過去に入力したデータを収集し、その人がどういった趣向なのかを、既に人工知能が知っていて、それを補助してくれるものや、長文の変換時における、変換候補の選出のアルゴリズムには本当に助けられている。これはインターフェースのこちら側に見えている記号の序列の話であり、その裏を走っているコードへの入力への反応としての他のコードの生成とは異なった文法なのであるが、どちらも原始的な記号操作の過程であるということを考えれば、盲目の思考にあてはまるだろう。
ヨーロッパでは、日本とは違い、死者の御霊は天に昇らず、そのまま身体とともに土葬されてしまうことが多い。しかし、言語がデジタル化され、身体感覚が麻痺していく現代において、結局、自然言語としての土に還ってしまうということなのかもしれない。
彼は、生という言語活動の中で、死という唯一の間違いを犯してしまった。
だが、彼の残した文章は、ウェブや本の中で、これからも永遠に生き続けるのだろう。
彼は、『薔薇の名前』や、私が持っている著作では、その後に出版される『フーコーの振り子』という長編小説でその名が知られているが、個人的には記号学者としての彼のほうに馴染みが深く、ソシュールや、チョムスキーを凌駕するほどの、その研究量における圧倒的な情熱において、私は虜にされたのであった。
その理由は列挙すればいとまがないが、記号学として、いち早くプログラム言語に焦点を当てているからというのがそのひとつ。以前とある論文で、彼の二進法的世界に於ける言語活動の探求過程について論じたこともある。
私はデザイナーだったので、プログラミングはほとんどやらないし、基本的なHTMLの語彙しか持ち合わせていないのだが、それらのコードの羅列が社会変革を起こし続けていることはまぎれもない事実であり、そしてそうなるであろうと未来を見通していた(先日の報道でもあったように、イタリア政府の見解には、「未来を予測した」という旨があり、これは「美学における天才性」としての敬意であろう)彼には、やはり先見の明があった。
ライプニッツから着想した彼のコードにおける思想は、それらの序列が天文学的な領野にまで到達するようなスケールであった。
彼は、著書『完全言語の探求』の中で、コードの序列は複雑で人工的な記号系を形成するが、知らない単語や推論におけるエラーなどが、コードとしての文章により算出され、補完されることによりそれらの穴埋めが出来るのではないかということを述べており、それをライプニッツに見ている。これが、いわゆる「盲目の思考」の一端である。数学的論理学としてのそれは、言葉に規定された内容から切り離された、意味論的ではない、「印」としての操作のルールを作成すれば、未知の世界へ我々を誘うというものである。
逆説的に言えば、基本的に人工言語は命令された文章(コード)にエラーを起こさないが、人間の文章にはエラーが起き、だからこそ人間なのだ、ということも出来る。これは特に自己防衛として書いているわけではないが、しょっちゅう間違いを起こす私のような人間でも、完全に機械から身体や脳を支配されたわけではないということを、認識できるのである。
しかし、エーコはそれらの副産物として、「個別的なもののカタログ化」という言葉を使い、それらの数学的に構築された情報の網の目により、「像」(現代で言うビッグデータ)が浮かび上がるとしている。
以前診断されたように、反復強迫だからなのか、ストレスからなのか、よく誤変換が起きる。しかし、現在は、GoogleIMEのような、ブラウジングや過去に入力したデータを収集し、その人がどういった趣向なのかを、既に人工知能が知っていて、それを補助してくれるものや、長文の変換時における、変換候補の選出のアルゴリズムには本当に助けられている。これはインターフェースのこちら側に見えている記号の序列の話であり、その裏を走っているコードへの入力への反応としての他のコードの生成とは異なった文法なのであるが、どちらも原始的な記号操作の過程であるということを考えれば、盲目の思考にあてはまるだろう。
ヨーロッパでは、日本とは違い、死者の御霊は天に昇らず、そのまま身体とともに土葬されてしまうことが多い。しかし、言語がデジタル化され、身体感覚が麻痺していく現代において、結局、自然言語としての土に還ってしまうということなのかもしれない。
彼は、生という言語活動の中で、死という唯一の間違いを犯してしまった。
だが、彼の残した文章は、ウェブや本の中で、これからも永遠に生き続けるのだろう。

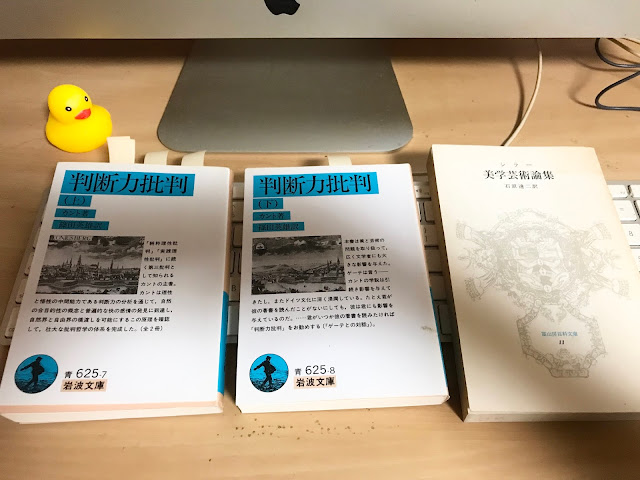
コメント
コメントを投稿