とある夏の日の釣行(と、魚達と人間の争いに関する見識)
それはとある夏の日、30℃を超えるモーレツな暑さと日照りのなか、突然起きたことだった。
私はいつも通っている小さな池で、頭のなかに蜘蛛の巣のように張り巡らされたタクティクスとメソッドをフルにカリキュレートしマインドをコンセントレートさせそのバンク沿いのオーバーハングのシェードのスポットへルアーをサイドハンドでキャスティングした。
すると、あれ、ルアーが動かない。一体どうしたのだ。また地球を釣ってしまったのか、それとも神の天罰が下って、「はやく研究に戻りなさい」という何かの合図なのかといった具合に、あるいは、ついに動物界が人間の能力を上回り、「あいつ、また同じルアー投げてら。こっちには全てお見通しだっつうの。ちょっと鰭で叩いて木にでも引っ掛けてやるか」と見透かされたのか、などという妄想が頭の中を駆け巡る。
しかし、その直後にその妄想は覆り、その得体の知れないものは確かにうごめいているということが竿から伝わってくるのであった。
竿先がグリップと比較し86.3度ほど曲がりこむ。リールは全く動かない。とにかく持っている竿にしがみついているのが必死であり、それは「魚に主導権を握らせない」というよく言われる台詞が完全に駄目になった瞬間でもあり、さらに、釣り糸の太さを計算すればこれ以上無理に引けない、つまり、にっちもさっちもどっちにもこっちにもいけない状態であった。
これが、開高健が言った「自然と人間との対峙」か!(『私の釣魚大全』参照)などとその時は考える暇はなかったが、とにかく対峙した。
そうこうしていると、その得体の知れない魚体が遂に観念したのか、寧ろそちら側から岸に寄ってくるではないか。私は魚の動きに反発することなく、寧ろ魚の言うとおりにロッドワークを働かせ、リールをリーリングし此方側へ誘導した。
すると、その得体の知れない魚体が遂に姿を現した。
これは正真正銘私が狙っていた、スズキ目サンフィッシュ科のブラックバスではないか。
後に計測してみると45cmアップの自己記録、その池のレコード記録には数センチ及ばないものの、記憶に残る魚となった。
ここに辿り着くまで長かった。自然との対峙というよりも、その一匹の魚と出会うまでの長い道のりを歩んできたわけだから、人生の物語におけるひとつのマイルストーンと言ったほうが正確かもしれない。
私は友達が多いわけでもないし、寧ろ自分自身で構築してきた方法論をひとつひとつ積み木のように組み立て、ついにこの瞬間に到達したのだ。これはジャン=ポール・サルトルでもわかるまい、ひとつの内在する精神との実存的格闘の末辿り着いた出来事でもあった。
私はその魚体に丁寧に水をかけ、口を抑え泳ぐのとは逆方向に動かして、エラに酸素を入れてやり、「ありがとう、またな」と挨拶をし、魚を逃してやった。
風景はこの釣行を無言で祝うがごとく魚と一体化し、青いカワセミはホバリングし、目の前を通り過ぎた。
そしてその大きな魚影は、ゆっくりと、物陰に隠れるようにして帰っていったのだった。
※TACKLE ROD: SHIMANO EXPRIDE 165L/2 BFS/REEL: SHIMANO ALDEBALAN+夢屋BFSスプール/LINE SYSTEM: SEAGUAR FLORO MEISTER 8lb./LURE: LuckyCraft B'Freeze SP
話は変わって生態系の保護に関する少々の考え方。
昨年、私が現在住む東北のY県において、コクチバス(スモールマウスバス)の繁殖及び捕食に関する対策として、県内の広域に渡るキャッチ・アンド・リリース禁止が発表された。これまでこのような対策は、長野県を始め全国で行われたが失敗に終わっている。
これはアングラーの立場、及び生態系の認識があまりできていないものと考えられる。この対策案は、主に放流した稚鮎を捕食しないようにするというものが漁協の意見及び県の考え方なのであるが、稚鮎は勿論川に放流する。だとすれば当然、川に生息するスモールマウスバスをゾーニングしてターゲットにすれば良い話なのだが、今回の対策は広域に渡る。つまり、リザーバーや野池等の、「鮎がいない場所」もそのゾーンに入ってしまっているのである。
そもそも、90年代に起きたブラックバス害魚論は論理的破綻が随所に見られ、根性論、或いはスティグマ化(負の連鎖)などが拡がり、本来、他の魚と共生しているエビデンスがあるにも関わらず、負のイメージが払拭しきれずにいる。
シマノプロスタッフである山木一人が以前『BASSER』誌(つり人社)で論考を述べたように、バスが日本に輸入され、約90年が経過した。海外から魚が持ち込まれるという考え方が悪いのであれば、この90年経った今、他の魚との共生している現状自体が「自然」であり、さらに、そもそも人間の手が加えられていない「本来の自然」など存在しない。
メタ・レヴェルで考えれば、「放流」自体が、人間が自然を壊している、あるいはコントロールしているということになる。勿論、鮎、ヤマメ等の他に、ブラックバスを漁協管理下のもと放流が許可されている湖も沢山あるのである。
これらの問題を捉えるうえでの第三項の考え方として、「人間生活も含めた自然に、人間の手が加わる部分と加わらない部分の線引」をどこに設けたらよいのか、という視点をここに提示しておく。



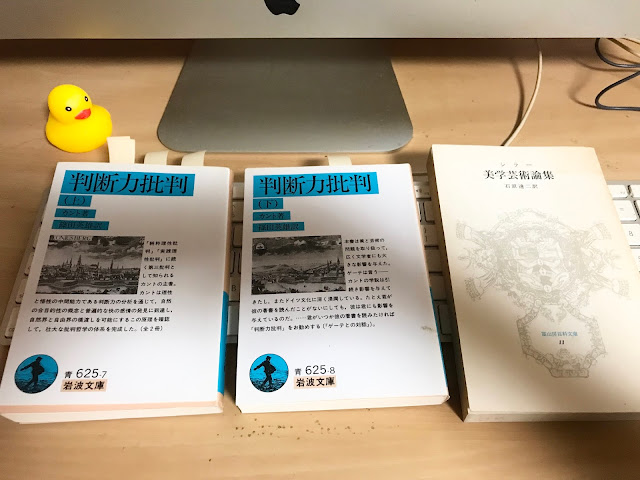
コメント
コメントを投稿