【デザインと思想】#1 消費行動変容――コロナ時代に読み返す『動物化するポストモダン』
5月25日、日本の新型コロナウィルス感染症に対する緊急事態宣言が全都道府県で解除された。しかし世界に目を向ければ、まだまだ収束には程遠い。また、政府が主張する「新しい生活様式」なるものが定着しなければ、第二波、第三波が訪れてもおかしくない。
このようなコロナ禍に思い出したのが、東浩紀『動物化するポストモダン』(講談社現代新書、2001)における「データベース消費」というキーワードである。この本は、近代の「大きな物語」――ジャン=フランソワ・リオタールや大塚英志が述べたような――を、主にジャン・ボードリヤールを援用し乗り越えようとした意欲作である。著者は主にアニメやキャラクターを論じているが、その理論は哲学・サブカルチャー批評を超えて、消費者行動論的なものにも引用されてきた。では、本題に移る。
ざっくり言えば、これまでは、「大きな物語」(CM、映画など)の延長上に商品があり、消費者はそのイメージで商品やサービスの購買へと流れてきたが、それに対する「データベース」の世界では、コードのDNA(デオキシリボ核酸)によって形作られた「モデル」に従って、直接消費者がECサイトなどのWEBサイトを通じて購買活動を行う、というものである。つまり、消費者は商品やサービスの「質が剥き出しになった」世界、つまりCMやポスターのイメージを経由しないで消費を行う、というものである(しかしながらテレビのもたらす影響は未だ大きい)。当記事を書いている一ヶ月ほど前はCMが無くなっていき、代わりにAC JAPANの動画がその穴を埋めるように放送され、外出はできないがAmazonではものが買えるということを経験したひとも少なくないだろう。これがデータベース消費の典型である。ただし、このブログは「デザイン」についてのものなので、これと何か因果関係があるのかと困惑するかもしれない。しかしここで大切になってくるのが、データベース消費の理論では、「WEBサイトや商品のパッケージがその商品イメージを決定的なものとする」、ということである。
このような事態をボードリヤールは「ハイパーリアリティ」と呼び、現実がITに取って代わられるということを後に記している(ボードリヤールはこれを1970年代に予言した)が、近年の第三次AIブームやレイ・カーツワイルのシンギュラリティ説などによって、人間が人間主体として生活することが機能不全に陥ることが警戒される。IT/AI/シンギュラリティに過度に執着することは要注意である。
とはいえ、IT技術がパンデミック時のインフラになっていることは事実ではある。ただし、少子高齢社会を迎えた日本では、いわゆる「デジタル・ディバイド」により、WEBサイトにすらアクセスできない高齢者が多いこともまた事実である。
何れにせよ、アフターコロナの生活様式のメルクマールを注意深く探っていきたいところである。
このようなコロナ禍に思い出したのが、東浩紀『動物化するポストモダン』(講談社現代新書、2001)における「データベース消費」というキーワードである。この本は、近代の「大きな物語」――ジャン=フランソワ・リオタールや大塚英志が述べたような――を、主にジャン・ボードリヤールを援用し乗り越えようとした意欲作である。著者は主にアニメやキャラクターを論じているが、その理論は哲学・サブカルチャー批評を超えて、消費者行動論的なものにも引用されてきた。では、本題に移る。
ざっくり言えば、これまでは、「大きな物語」(CM、映画など)の延長上に商品があり、消費者はそのイメージで商品やサービスの購買へと流れてきたが、それに対する「データベース」の世界では、コードのDNA(デオキシリボ核酸)によって形作られた「モデル」に従って、直接消費者がECサイトなどのWEBサイトを通じて購買活動を行う、というものである。つまり、消費者は商品やサービスの「質が剥き出しになった」世界、つまりCMやポスターのイメージを経由しないで消費を行う、というものである(しかしながらテレビのもたらす影響は未だ大きい)。当記事を書いている一ヶ月ほど前はCMが無くなっていき、代わりにAC JAPANの動画がその穴を埋めるように放送され、外出はできないがAmazonではものが買えるということを経験したひとも少なくないだろう。これがデータベース消費の典型である。ただし、このブログは「デザイン」についてのものなので、これと何か因果関係があるのかと困惑するかもしれない。しかしここで大切になってくるのが、データベース消費の理論では、「WEBサイトや商品のパッケージがその商品イメージを決定的なものとする」、ということである。
このような事態をボードリヤールは「ハイパーリアリティ」と呼び、現実がITに取って代わられるということを後に記している(ボードリヤールはこれを1970年代に予言した)が、近年の第三次AIブームやレイ・カーツワイルのシンギュラリティ説などによって、人間が人間主体として生活することが機能不全に陥ることが警戒される。IT/AI/シンギュラリティに過度に執着することは要注意である。
とはいえ、IT技術がパンデミック時のインフラになっていることは事実ではある。ただし、少子高齢社会を迎えた日本では、いわゆる「デジタル・ディバイド」により、WEBサイトにすらアクセスできない高齢者が多いこともまた事実である。
何れにせよ、アフターコロナの生活様式のメルクマールを注意深く探っていきたいところである。


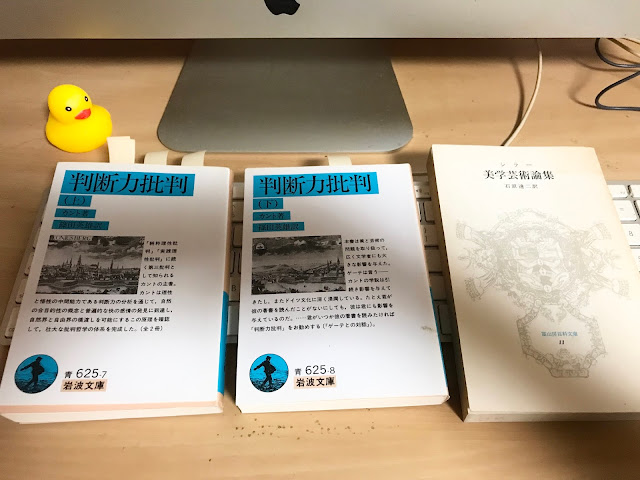
コメント
コメントを投稿