送り返される無の眼差し――エドゥアール・マネvs.ジェフ・ウォール
ジャン・ボードリヤールが評価した芸術家の一人にマルセル・デュシャンがいる。その理由は言うまでもなく「レディ・メイド」の手法が産業におけるシミュラークル(註1)、つまり既製品を用いた美術のゲーム化に成功したから、あるいは美術制度に対するラディカルで批判的な態度によるものだろう。この、1913年に《自転車の車輪》から開始されたレディ・メイドから、コンテンポラリー・アートや反芸術への現在までの連続性があるとされている。勿論、それらは紛れも無い「出来事」であり、事実であるのだが、それより31年前に、より根源的なもうひとつのゲームが始まっていた。それは、エドゥアール・マネが《フォリー=ベルジェールのバー》を描いたことに起因する。実は、この絵画には、とある仕掛けが施されている。
絵画の舞台は、パリ郊外、フォーブール・モンマルトル通りのほど近くにあるバー、フォリー・ベルジェール。中央に佇むバーメイド、手をつくカウンターには酒、果物の静物画があり、その背後には大きな鏡と騒然とごったがえす観客、そしてバーメイドと話をする男が映し出されている。しかし、本来ならば、鏡の中央に映っているはずのバーメイドと男は、タブロー向かって右にずらされたように描かれている。
これは一体何故なのか。哲学者・小林康夫は、ミシェル・フーコーの講義テクストの解読を通して、「〔…〕古典的な絵画が遠近法の効果によって、絵が見られるべき視点を一点に定めていたのに対して、マネの絵はそうした規制を排除して、絵画が指定する視点に見るものが場所を同定することなく、言わば見る者がタブローの周りを自由に歩き回れるような「絵画=オブジェ」を打ち立てた〔…〕」(註2)としている。マネの絵画がルネッサンス以前の絵画の価値転倒を代理表象すること、またタブロー内での遠近法の無化における平面化や、そのあえてスキャンダルを呼び起こす構図はこれまで幾度となく議論されてきた。しかし小林は、このフーコーのマネに対する読解が不十分であるとし、次のように論旨を展開する。「〔…〕かならずしもフーコーが講演のなかで主張していたように、タブローに対して見る者の視点が移動可能であるようにし、タブローという絵画の支持体の現実性を強調するためではなかったのではないか。むしろ、それは、女人柱のように堂々としたこのバーメイドに、キャバレーという喧騒たる風俗の場処には似つかわしくないようなある種の聖性あるいは至上性を与え返すためではなかったろうか。」(註3)と。さらに、「周囲の喧騒から隔絶されて、たとえ一瞬のことにしても、彼女はまさにバタイユが言うような「深いアパシー」の眼差しをこちらに差し向けているのだ。」(註4)としている。
つまり、空間や、観るものの視線をずらす行為は、周囲の喧騒から、この美しいバーメイドを引き離し、さらに女人柱から注がれるアパシー、つまり「無の眼差し」のためだったのではないかと論じている。聖性や至上性をジョルジュ・バタイユ的に読み解いているところからは、バタイユがマネを古い価値観を乗り越えるための「供犠」として捉えたことによるもの、また「供犠」は「俗」を超えなければならないとしたことから由来していると考えられる。
この「供犠」と「無の眼差し」の視線の先には、一体何があるのだろうか。
逆照射
とある写真を見ていただきたい。これは、ネオ・コンセプチュアル・アート/シミュレーショニズムの写真家・ジェフ・ウォールの作品《女性への写真》(©jeff Wall Courtesy Marian Goodman Gallery, New York )である。
この作品は、紛れも無く前述のマネ《フォリー=ベルジェールのバー》への約100年を隔てた末の返答としての作品である。(註5)この写真におけるカウンター、人物の配置、そしてカメラはその構図を模倣しており、アプロプリエーションとしての手法が見做される。この作品における批評言説は、美術史家、デヴィッド・カンパニーや、テート・モダンでの個展開催時におけるものなどが存在するが、どれもさほどのものではなかった。つまり、それらは単なるサンプルとしてマネを借用しているというものであった。では、この写真の本質は何処に潜んでいるのであろうか。
まず、写真を撮る側である「主体」(註6)について。カメラにより視線を送り返し、撮影しようとしているウォール本人は写真右に位置しており、味気ない表情をしている。無論、この位置取りは《フォリー=ベルジェールのバー》の紳士のそれに対応している。(一見)撮影者であり、作者の手には、カメラのリモートスイッチが握られており、彼がシャッターを切ろうとしているという演出が見て取れる。勿論、ウォールの写真は、風景写真等を扱うアーティスト・写真家の写真ではないため、この演出自体についてはそもそも問題ではない。確認だが、紳士は、絵の中では鏡に映っているが、バーメイドの視線とは無関係になっていた。そしてこの写真自体、ウォール以外の第三者が撮っている。というか、撮らなければこの作品自体が物理的に存在しない。さらに、部屋が明るいということは、写真を撮ろうとしていないということであり、それはつまり、主体であるウォールは「写真を撮っていない」ということになり、要するに、マネにおける紳士と対峙させるように、自らを無化してしまったのである。
合せ鏡
では、この写真を撮っているのは誰か。もう一度、《フォリー=ベルジェールのバー》を振り返る。この絵の最大の特徴は、タブロー全体に描かれている大きな鏡である。この鏡に映し出されている光景は、もはやバーの喧騒の中の大勢の客や、帽子を被った紳士ではない。この鏡が写したものは、《女性への写真》そのものではないか。
つまり、ウォールの《女性への写真》はこの鏡によって「撮られた」という出来事なのだ。さらに、この鏡がカメラにおける「プリズム」の役割を果たしていると考えれば末恐ろしい。この二つの絵画は、鏡と、またそれに対応するカメラ内部の鏡との「合せ鏡」になっている。
要するにこのことは「死への欲動」を表しており、その上、バタイユの言う「供犠」としての芸術となった。そう考えると、なぜ写真に映る女性が怒りや狂気に満ちたような顔をしているかがわかる。ジェフ・ウォールは、コンテンポラリー・アートにおけるゲーム、あるいは写真を、他の誰よりも前進させたと言って、もはや過言ではないだろう。
新たなる写真へ
デジタルカメラが発明され、携帯電話にカメラが付いてからというもの、写真はアナログな「現実性」を奪われ、もはや超現実空間としてのインターネット上に流布する写真は出来事ではなくなった。それは、「写真は一度きりしか起こらない」という前提を覆し、無限に反復され、時間まで操作可能な事態にしているからだ。Instagramには毎日無数の写真が投稿され、投稿する誰もが「芸術家のような」写真を取り、芸術家とアマチュアの差異はどんどん消失している。何か物悲しい事態ではあるのだが、しかし、しばらくは写真家とアマチュア写真家は共存しうるとも考えられる。
なぜなら、現在のアマチュアは、デジタルカメラのモニターやフォトフレームで写真を観ているのに対し、プロの写真家はそれをアウトプットして「モノ化」しているからだ。
プロの作品は、超現実のネットワークから分離された時に、「機能」との隔絶が起き、つまり主体に対して相対的になった物(註7)なのであり、それらは情熱的な収集家、あるいはギャラリーに買い取られ、さらにそれらは全体のシリーズ(註8)を構成しなければならないために、収集家はさらに収集せずにはいられないのだから。
他方、アマチュアの写真は、もはや光やモノとは関係なくそれらは「連続性=複数性」(註9)のもとインターネット上にばら撒かれ続ける。しかし、これらは全く無秩序なわけではなく、「「テーマ別の」連続場面として積み重なるあらゆるイメージ」(註10)つまり「タグ」としてこれからも集積されて行くだろう。
ボードリヤールが指摘しきれなかった差異はこの点にある。しかしこれは、ネガという概念が無くなったこと、つまり強いて言えば最初の一回の物質性が無くなったことに起因する「だけ」なのであり、完全に写真としての物質性が無くなるということは想定しにくい。データベースやハードウエア上に保存し、その内部で閲覧ができたとしても、またそれらが液晶や、将来的に有機ELディスプレイ上に展示されたところで、それらの機械が壊れてしまっては、写真自体が無くなってしまうのだ。
〔…〕その写真のなかに、現実がその映像の性格をいわば焼き付けるのに利用した一粒の 偶然を、凝縮した時空を、探しもとめずにはいられない気がしてくる。その目立たない場、もはやとうに過ぎ去ったあの数分のすがたの中に、未来のものが、今日もお雄弁に宿っていて、われわれは回顧することによってそれを発見することができるのだから。(註11)
かつて、ヴァルター・ベンヤミンがこのように語ったように、写真を観る欲望は衰えないだろうし、写真は残り続けるだろう。そして、1880年以降に失われたアウラをなおも存在するかのように(註12)様々な手法が写真表現を強化するのだろう。それはまさに前述の《女性への写真》のような、操作されたアーティストの写真のようなものもその一形態である。視覚的無意識(註13)としてのシミュラークルの全面化は、現代ではサイバースペース上のシミュラークルの総量が増えすぎたために、なぜかポスト・モダン以前に戻るようにモノの一回性に回帰しているように見えてならない。
SNSの喧騒を見ては溜息が出る。しかし現時点で、超現実世界は無(null)ではない。我々は、あのバーメイドのような無の視線(apathy)のように、物憂げにその絵を見つめなおし、またサイバースペースに落ちている、沢山の画像の断片の中を、今日も散策してしまう。
(註1)シミュラークル=本物のないコピーの意味。ジャン・ボードリヤール『シミュラークルとシミュレーション』、法政大学出版局、2013、参照。
(註2)小林康夫『表象の光学』、未來社、2003、98頁。
(註3)同書、102頁。
(註4)同書、102頁。
(註5)『現代アート辞典』、美術出版社、2012、109頁、参照。
(註6)ここでの「主体」と「客体」の関係は、「撮る者」と「撮られる者」という意味で、カメラ・オブスクラにおける物理的特性を指す。ロラン・バルト『明るい部屋――写真についての覚書』、みすず書房、2009、17頁。
(註7)ジャン・ボードリヤール『物の体系』、法政大学出版局、1984、106頁。
(註8)同書、106頁。
(註9)ジャン・ボードリヤール『なぜ、すべてがすでに消滅しなかったのか』、筑摩書房、2009、35頁。
(註10)同書、35頁。
(註11)ヴァルター・ベンヤミン『複製技術時代の芸術』、晶文社、1999、64頁。
(註12)同書、72頁。
(註13)ベンヤミンの用語。一回性の消滅により、時間的脱臼がおこること。ヴァルター・ベンヤミン『写真小史』、ちくま学芸文庫、2013、17頁、参照。



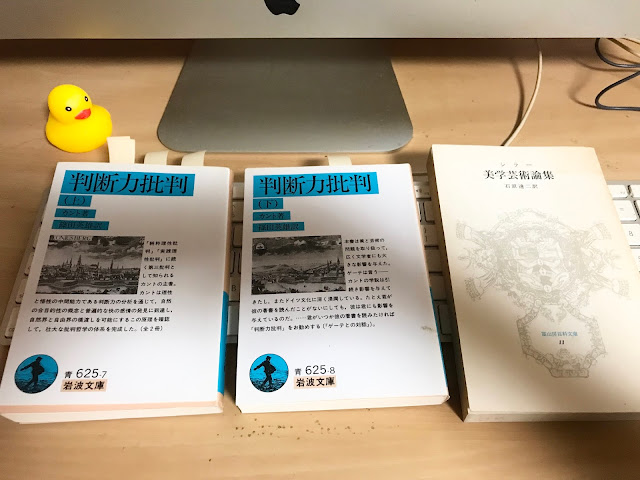
コメント
コメントを投稿