リチャード・ブローティガンにおける「意味論」と「官能」
Richard Brautigan, last of the beat. Olivier Dalmon, CC BY-SA
「二つの墓地には隣りあって、それぞれが小高い丘の上にあった。二つの墓地の間を、墓地クリークが流れていた。いい鱒がたくさんいて、夏の日の葬送行列のように緩やかに流れていた」(R.ブローティガン『アメリカの鱒釣り』、「墓場の鱒釣り」、新潮文庫、藤本和子訳)
ブローティガンはこの『アメリカの鱒釣り』で、ビート・ジェネレーションの作家・詩人として、世界中にその名が知れ渡るようになる。
「ここにすばらしいものがある。
きみがほしがるようなものはぼくには
殆ど残っていない。
それは君の掌のなかで初めて色づく。
それはきみがふれることで初めて形となる。」
(『突然現れた天使の日』、「ここにすばらしいものがある」、思潮社、中上哲夫訳)
この他にも、エロティシズムや弾丸のように放たれた文章が数多く存在し読者を今も魅了し続けている。先日邦訳された『ブローティガン東京日記』も話題である。東京日記は本人曰くアルケオロジー(考古学)的に書かれたという発言も残っている。
ここでは邦訳版『アメリカの鱒釣り』に書かれている、柴田元幸の「アメリカの鱒釣り革命」に倣って、同時代に出版された、柄谷行人『意味という病』に接続させてみよう。
「[......]つまり、精神という場所ではどんな奇怪な分裂も倒錯も生じるということをあるがままに認めたところに、彼の比類ない眼がある。この眼は、人間の内部を観察しようとする眼ではない。観察したり分析したりするには、この自然はあまりに手強い。いや手強いからシェークスピアはそれを自然と呼んだのである」(柄谷行人『意味という病』)この章はマクベス論、蛇足だが、世の中はシェークスピア没後100年ということで盛り上がっているが、そこには触れない。
柄谷は同書において、「意味や内容には還元できない核心があった」とする。まさにそれを体現していたのがブローティガンであった。


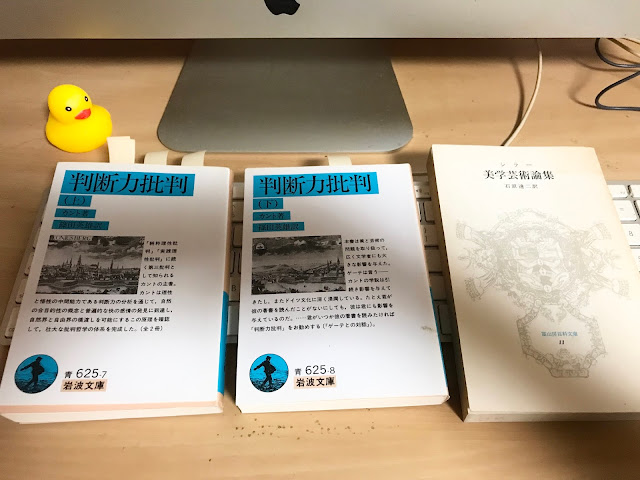
コメント
コメントを投稿