道
ひとが、未開の地へと足を運んでみたいという願望、あるいは人生の比喩として、「道」というものはつくられ、存在する。「空想の道」、現実のその既に「道」としてある上を歩く「道」。
私事ではあるが、様々なジャンルに足跡を残そうと苦心した。ときにその迷宮に戸惑い、斜めに、仄暗い「茨の道」を歩んできた。そして歩もうとする「意思」を何度も転んでは起き上がり奪取してきた。
そのような、特に人生論をだらだらと語ろうという気はないのですが、何か人間の心に不安や安堵がパラレルし内在するものを具現化した作り手たちそれぞれの「道」を、今回は領域横断的に紹介しようと思います。
” I am the stranger. The path is my story. I walked the twisted miles towards my dream. I walked the grey path of shadow and glory, The granite moorland and the moorland stream. I walked the twisted miles towards my dream, Undaunted as I climbed hope’s granite tor. The granite moorland and the moorland stream, They drew my steps towards a distant shore. Undaunted as I climbed hope’s granite tor, I saw far clouds of lightning at the dawn. They murmured I would walk for evermore. Born with no future, my future was born. "
つまり大まかに要約すれば、道はわたしの物語。夢に向かって、捻れてしまった灰色の道を、そして栄光と表裏の影の道を、靴と共に歩んでいく、という自然の崇高の表現を用いた構成。
私事ではあるが、様々なジャンルに足跡を残そうと苦心した。ときにその迷宮に戸惑い、斜めに、仄暗い「茨の道」を歩んできた。そして歩もうとする「意思」を何度も転んでは起き上がり奪取してきた。
そのような、特に人生論をだらだらと語ろうという気はないのですが、何か人間の心に不安や安堵がパラレルし内在するものを具現化した作り手たちそれぞれの「道」を、今回は領域横断的に紹介しようと思います。
東山魁夷《道》1950年
東京国立近代美術館蔵
東京国立近代美術館蔵
「この道の作品を描いている時、これから歩いてゆく道と思っているうちに、時としては、いままでに辿って来た道として見ている場合もあった。絶望と希望とが織り混じった道、遍歴の果でもあり、新しく始まる道でもあった。未来への憧憬の道、また、過去への郷愁を誘う道にもなった。」(魁夷)
この、誰もが知っている東山魁夷の《道》は、過去と未来との時間の連結を、魁夷自身が述べるように、「象徴の世界の道」として描かれた。青森県種差海岸のとある牧場がこの絵画の舞台。魁夷は十数年前のスケッチから想起し、実際にその地に足を運び、そして、牧場であるその場所で、辺りの枯れ草などを取り除き、「象徴」の風景として、タブローの中に閉じ込めた。紛れもなく、それは人生というひとのこころに内在する象徴として描かれている。
その「未来への憧憬」は、空が敢えてちいさく描かれ、消失点をタブローの上方に向かって描いた構図からも伺え、さらに「遠くの丘の上の空を少し明るくして、遠くの道が、やや、右上りに画面の外へ消えているようにすると、これから歩もうとする道という感じが強くなってくる」と魁夷が述べるように、まさに未来へと伸びる「象徴としての道」がそこにある。
枯れ草は緑に塗られ、タブロー全体をあえて抽象的なぼかしを使い描くことで、まるで夢の中に出てきたような映像の断片のようである。それは恐らくかれが、15年前にそこでスケッチした原画から、「そこに再び旅したい」という現実ではない「夢」の世界としての表現なのかもしれない。あるいは、魁夷自身の頭の中にあった、フロイトで言えば抑圧された象徴ということになるでしょうが、そのようなものが、絵画として、現実の中に描かれたのだ。先程述べた通り、このパースは、未来や、その消失点の中心(つまり神秘的な)方向に向かって伸びている、むしろ極めて前向きな人生観としての象徴であるということが出来るでしょう。
また、魁夷が道の思い出の例として挙げ、「人生の寂寥」を表しているというシューベルトの「冬の旅」もここに載せておきます。
ジャンルは変わり、古典の次はジャズ。Igor Gehenot Trio(イゴール・ゲノー・トリオ)の「ROAD STORY」より、「Lena」。
若いこのベルギー出身のトリオはつい数年前にこのアルバムを出し、名声を集めることとなる。ハービー・ハンコック的なピアノの美しい旋律、シンコペーション、そして何よりも(アルバムジャケットも道路沿いを3人が歩く写真なのだが)薄暗い道、あるいは闇を切り裂いて、細々と、しかし力強く歩こうという意思がこの曲からは感じられます。
多少ジャンルや時代が大きく飛んだが、アナクロニズムとして解釈してもらって構わない。次はまた大きく跳躍して、靴について。
ここでひとつのとあるプロモーション・ビデオを観てもらいたい。
こちらは、ロンドンの老舗靴店、John Lobbのビデオです。この映像では次のようなことが語られている。
つまり大まかに要約すれば、道はわたしの物語。夢に向かって、捻れてしまった灰色の道を、そして栄光と表裏の影の道を、靴と共に歩んでいく、という自然の崇高の表現を用いた構成。
ここでは、革やその裁断などの作り方などには踏み込まない。しかし重要なのは、人生はただ単に、メディアに溢れる虚構に満ちたきらびやかなものではなく、もっと陰鬱で、しかしその中からなにかをつかもうとするものでもあるということ。
上掲の写真は、私の自宅にある靴。これまでの人生を「共に歩んできた」靴達(左からCONVERSE All Star、Dr. Martine、そしてついに手に入れてしまったTricker's)。CONVERSEとDr. Martineはバンドマンや、その聴取者のシンボル(CONVERSEは元々バスケットボール用のシューズ、Dr. Martineはマーティン博士が工場労働者が足を怪我した際にゴム底にしてそのショックを和らげようとしたという歴史がある)になっています。ここにジョン・フレデリック・ペリーの月桂樹と、ボシュロム・オプティカルが開発したパイロット用のサングラスであるRay-Ban、そしてターゲットマークが揃えばモッズ(ロック)ファッションの出来上がりなのですが、これも話の文脈から脱線してしまうのでこれ以上書きません。
前述した人生の「陰鬱」は、写真では判別の仕様がないが、靴底のすり減り具合に表れる。素材は違えど、CONVERSEとDr. Martineのソールはゴム。そしてTricker'sは木板の合板。特にDr. Martineはこれまで幾度となく酷使され、底はもとより、インソール、そして革も劣化してしまいました。
「人生という道」を共に歩んできた「相棒」としての靴。自分で言ってしまえばその苦労は、そのひとそのひとの靴底の減り具合が物語る。
しかし、未来へと開かれた次の一歩を踏み出すために、靴というものは存在する。そしてつかみとらなければならない。でなければ靴などはなから要らない。
ただし、多少のポエジーを挟めば、そのひとの軌跡はすぐに目に見える足跡となり、振り返れば、そこに残っている。そこには時間としての「過去の点」、あるいは「痕跡」が、引き伸ばされ、残っているのです。
時代と領域がジャンルレスに語られくらくらしますね。今度は車です。
これは記憶が正しければ2014年の新春に放映されたBMW電通(?)によるBMW X5のCMです。
特にBMWが好きなわけではないですし、私自身はCITROEN 2-CVなどのクラシックカーが
好みなのですが、ここでは「あなたの道は開ける」というコピーに着目します。何と言ってもこのコピーの力強さは、ドイツ車ならではの高剛性ボディとレスポンス、そしてBMWが誇る直列6気筒エンジン(シルキー6)によるパワフルな加速が裏付けています。
話題が車ですので、人間の移動の道具。さきほどの人間の足跡の話からの「人体の拡張」あるいは「行動範囲の拡大」ですね(先程の足跡の写真にはタイヤの轍も入れておきました)。「リスペクトされる、それは才能だ」という台詞が挿入されていて、少々上から目線な感じもしますが、CMが高級車なのであればそれはいたしかたない。道は開けるというのは「モーセの十戒」などを想起させますが、その質実剛健さは、そのプロダクトが証明している。
つい先日、HONDAがGoogleと自動運転技術における技術提携をするという話を耳にしました。Googleが自動運転のA.Iを載せたプリウスをパロ・アルト周辺で試験走行しているということ、あるいはTESLA MOTERSがコンピューターと運転技術を融合させるというコンセプトのもと研究開発をしていることは周知の事実ですが、ドライビング・プレジャーという面においては、まさにBMW社のブランド・タグラインである「駆け抜ける歓び」、つまり人間が運転する楽しさというものとは遠くはなれてしまう気がしますし、もしくは、人工知能が人間を支配するという、ある意味、映画「MATRIX」的な「シンギュラリティ問題」としての倫理問題も考えざるをえない。車は人間の「新しい足」なのですから。
私自身、今現在、人生の岐路。Y字路のようなところ。即ち分岐点に立っている。これから先どうなるかわからない。
横尾忠則© Y字路シリーズ《暗夜行路N市-I-B》
作家の意図から切り離して解釈すれば、そのような不安を表しているとしか考えられない一枚の絵画を最後に提示しておきます。横尾忠則の有名な《Y字路》です。暗闇の中にネオンのような、または惑星のようなモティーフ、そしてゴッホを連想させるような、タブロー全体に描かれる鬱々とした線(ゴッホは鬱病に悩まされていました)。左は真っ直ぐに伸びた道路ですが、右に行けば入り組んだクランクのようになっている。とすれば、わたしは左に行きたい。しかし、行けるかどうかもわからない。その内在的な不安をこの絵が表現してくれているとしか思えないのです。
それは私だけの問題ではない。私の魂の半分が預けられるひと、あるいは、この暗闇の奥でさらに険しくなるであろう「道」を、「力強く」、そしてリズムから派生する「グルーヴ」として受け止め、未来へ向かって前進しなければならない。それがまさに、道を踏み出す「今」なのです。





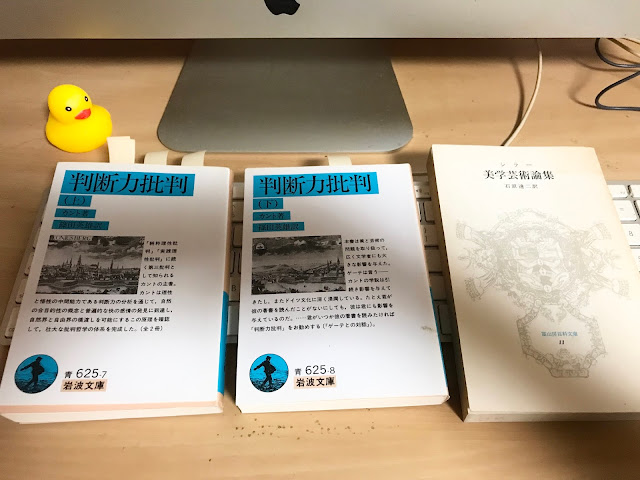
コメント
コメントを投稿