エアリプライとストレス
ソーシャルメディアが浸透してからというもの、各々が、各々のメディアを持てるようになった。それはこれまでの、マスメディア的で一方通行なバイアスがかった情報から解放され、よりパーソナルな、細かくて精度の高い情報を発信していくことが可能になったというメディア環境の変化を意味している。本当に簡単に良い所を言うと、そういう事で。これはメディア論の大家、マーシャル・マクルーハンの言うところの「ホットなメディア」が増えたということだと、極私的に理解していた。使い方によっては、良い効果を沢山生み出せる。
しかし最近ソーシャルメディアを俯瞰して見ていると、所謂有名人たちが誤った批判にあったり、それに怒ったりを繰り返している姿が散見される。これは一体どういうロジックなんだろうと、色々と考える機会があり、そうこうしているうちに、自分もそういったことに多少なりとも巻き込まれ、ああそういえばと、ちょっと前に自分が遭遇したことを思い出したのだった。だから今日は、それがどういうことだったか、きちんと明らかにしていこうと思う。
「エアリプライ」という言葉をご存知だろうか。
例えばTwitterでは、本来@(メンション)とか、RT(リツイート)等といったやりかたである特定の個人に対してリプライ(返信)をする。Facebookの場合は、個人のコメントに対してコメントを返す。
しかし「エアリプライ」の場合、タイムライン上で、不特定に向けてそのやり取りを行うことになる。
それは、内容がポジティブなことであれば面白い場合もあるし、個人を応援することも出来るが、他人のことを隠喩したり、罵ったり、罵倒したりされれば、気分が悪い。自分のことに対して言っているのかどうかをあえてぼかすケースもあり、それも精神的によくない。
つまり、まさにそういったことがTwitterで行われ、学生の頃、炎上のような事態に発展したことがあったのだ。
事実の概要を以下に記すとこうなる。
1.まず、「うぜぇ」だとか、「メンヘラ」だとか、「キモい」だとかいった言葉が自分に対してエアリプライであびせられる。これに対して苛立たない人などいないだろう。
2.そういったことが常習化してくると、苛立ちを抑えられなくなって、我慢できなくなり、私自身もそれに対してエアリプライで怒ってしまう。
3.それを見ている周りの不特定多数のフォロワーは、「もしかしたら、自分に対して言っているのではないか?」という気になり、全くそんなこと思ってもいないのに、言われている別人からも罵倒があびせられる。
基本的に、上記のようなカタチが繰り返され、事態が拡大していく。
本来メディアの相乗効果は、様々なステークホルダーを渡って縦の螺旋を描き、少しずつ登っていくのだが、こういう場合、逆の螺旋を描いていく。
こうなると、もう完全に怒っている私自身が「ワルモノ」と見られ、非難の対象と化してしまうのだ。フォロワーは、自分が発しているメッセージの対象が良く見えないので、意図や文脈が、事実の核心から永遠とズレていってしまうのだ。だから私自身からすれば、言われていることは的外れに映ってしまう。
事態が進行すると、「地獄に堕ちろ」だとか、「もう生きられない」などといったことを言われ、さらに永遠と侮辱してくる匿名アカウントを作成され、自分の写真をどこかから拾ってきて、それをPhotoshopで、まるで薬物中毒者のような顔に加工され、自分の身体特性まで侮辱され、意味不明な言説で、誹謗中傷してくるといったこともあった。中傷をしてくる人は、それをけむにまいて、その周辺の人を見方に付け、煽ったり、知らんぷりをしたりした。そしていっこうに謝ろうとしない。さらにちゃらけた言動で「拡大解釈だ」などといって、事態を収拾しようとしていた。本当に腹立たしい。
これは、投稿するたび承認を繰り返し、自己から発せられたメッセージが自己に帰属するというソーシャルメディアの特性からすれば、罪悪感や、集団から排除された気分に陥り、もうやっている意味がそれこそ無くなるので、一旦辞めるに至った。
さらに、これがリアルを浸食する。信頼している恩師と飲んだ時も、もっと静かにしろと怒られた。なんで他人に対して色々言うのかと。その時は、それを説得する力も残っておらず、ただただ家に帰っては落ち込むという日々が続いた。「言葉は剣ではない」などと一線のコピーライターから言われたこともあるが、正直、コピーライターの学校にも通っていたし、そんなこと分かっていた。そんなこんなで、一定の信頼を失ってしまい、イメージも低下した。様々な方法でそれらの回復を試みるが、なかなか難しい。
最終的には鬱になり、病院に通ったりもした。まだ正直、体調は良くないが、良くないなりに、頑張ってやっている。
勿論、私自身が完全に正しい言動をしていたかは定かではない。当時のモノの見方や知識に、幼稚な点はたくさんあったと思うし、まだまだ現時点でも知らないことは沢山ある。
ただ、こういったことは、世の中が許さないものだと思っていた。しかしながら、そういった事実が確かにあった。
ただ私は、本来人同士は共生しないと生きられないということを知っている。なので、そういうことを私にしてきた人達も、それぞれのことがあるんだし、あえて名前は出さないことにした。
おそらくまた「過去を振り返るよりも、未来へ向かって前進しろ」といったことや、「なんで今さら」などといったことを言われるかもしれない。けれど、こういうことを明白にしておく必要があった。
さて、これを読んだ人の苛立ちは、どこに向かえばいいのか。それは、こういったことを二度と繰り返してはいけないという社会をつくって行くということに向かうべきなのではないだろうか。そして私自身もそう願っている。
私はまだ駆け出しだけれど、フリーのデザイナーです。なので、コミュニケーション・デザイナーやプランナー、研究者などからすれば文章や理論の腰は弱いかもしれない。けれど、私なりにこういった事態を経験したことを通して見えてきた様々なことがあるので、それを世の中のために活かしてもらうために、以下にそういった事態が起こる悪いパターンや現象を書こうと思う。
まず、こういう場所での言葉は、一人ひとりが抱えている、それぞれの集団に依存してコード化されることが多いんじゃないかということ。つまり、見ている人にとって、その発言がおかしいと思うことでも、その人の集団では、正しいことだったりするということ。だから、一概に「それはぜったいだめ」などとステレオタイプなどでレッテルは張れない。またアカウントの使用のしかたが「オープン」か「クローズ」かでも、違ってくる。
次に、「無意味に罵ること」と、「指摘すること」「批評すること」は、リアルな社会でも、WEB上でも本来違うということ。明確に区分された自明なことであるということ。ただこれは、五感を使ったコミニュケーションで成り立ちやすいことで、WEB上では、表情や身振り手振りなどのボディーランゲージがなかなか出来ないのでこれの区分は成り立ちにくく、「意味」だけが流布しやすい。リアルにはコミニュケーションのクッション材のようなものがあって、それがWEB上の社会にも、戻ってきてくれることを願ってやまない。
さらに、スマートフォンなどのデジタルメディアと人体は切っても切れない関係になっているということ。共同体意識はそれによって各々の思想や場所などによって個人化し、それぞれの場所で、それぞれの公共意識をつくる。リアルとバーチャルが平行世界でコミニュケーションが成り立っているというより、バーチャルなネットの人格がリアルの方に侵入して来ているんじゃないかということ。だから、WEB上で罵られたことは、リアルでも罵られるということ。それが、家の内と外、電車などの公共空間、道端など、どこまででも着いて来て、これまでの「そこにいったらその集団」といった具合ではなく、「いつでも、すべての集団と一緒にいる」となるのではないかということ。
最後に、批判するなら個人のことなどではなく、問題を批判して、それを問題解決に結び付けなければいけないということ。
頑張って、まずは自分を振り返って、自分のことをやらなきゃいけない。
勿論、〇〇はダメ、とばかりも言っていられないので、僕自身、何言われようと未来に向かって頑張らなきゃいけないな、とも思ってる。この間、駅貼りの広告で知って、感動したコピーがあるので、載せておきます。
「未来にタネをまこう」
グランドスラム、世界No.1への道。
僕にはまだ見えない。
だからまだ、夢が見られる。
http://www.jaccs.co.jp/cm_miraini2/index.html
P.S.
今、東京の下町に住んでます。
下町のおっさんやおばはんは、何か嫌なことがあると、
「んなもん、ずっと気にしてたってしょうがないぜ。気にせずやれや。」と勇気づけてくれる。
こういう世の中に、早くもどらんかな。
しかし最近ソーシャルメディアを俯瞰して見ていると、所謂有名人たちが誤った批判にあったり、それに怒ったりを繰り返している姿が散見される。これは一体どういうロジックなんだろうと、色々と考える機会があり、そうこうしているうちに、自分もそういったことに多少なりとも巻き込まれ、ああそういえばと、ちょっと前に自分が遭遇したことを思い出したのだった。だから今日は、それがどういうことだったか、きちんと明らかにしていこうと思う。
「エアリプライ」という言葉をご存知だろうか。
例えばTwitterでは、本来@(メンション)とか、RT(リツイート)等といったやりかたである特定の個人に対してリプライ(返信)をする。Facebookの場合は、個人のコメントに対してコメントを返す。
しかし「エアリプライ」の場合、タイムライン上で、不特定に向けてそのやり取りを行うことになる。
それは、内容がポジティブなことであれば面白い場合もあるし、個人を応援することも出来るが、他人のことを隠喩したり、罵ったり、罵倒したりされれば、気分が悪い。自分のことに対して言っているのかどうかをあえてぼかすケースもあり、それも精神的によくない。
つまり、まさにそういったことがTwitterで行われ、学生の頃、炎上のような事態に発展したことがあったのだ。
事実の概要を以下に記すとこうなる。
1.まず、「うぜぇ」だとか、「メンヘラ」だとか、「キモい」だとかいった言葉が自分に対してエアリプライであびせられる。これに対して苛立たない人などいないだろう。
2.そういったことが常習化してくると、苛立ちを抑えられなくなって、我慢できなくなり、私自身もそれに対してエアリプライで怒ってしまう。
3.それを見ている周りの不特定多数のフォロワーは、「もしかしたら、自分に対して言っているのではないか?」という気になり、全くそんなこと思ってもいないのに、言われている別人からも罵倒があびせられる。
基本的に、上記のようなカタチが繰り返され、事態が拡大していく。
本来メディアの相乗効果は、様々なステークホルダーを渡って縦の螺旋を描き、少しずつ登っていくのだが、こういう場合、逆の螺旋を描いていく。
こうなると、もう完全に怒っている私自身が「ワルモノ」と見られ、非難の対象と化してしまうのだ。フォロワーは、自分が発しているメッセージの対象が良く見えないので、意図や文脈が、事実の核心から永遠とズレていってしまうのだ。だから私自身からすれば、言われていることは的外れに映ってしまう。
事態が進行すると、「地獄に堕ちろ」だとか、「もう生きられない」などといったことを言われ、さらに永遠と侮辱してくる匿名アカウントを作成され、自分の写真をどこかから拾ってきて、それをPhotoshopで、まるで薬物中毒者のような顔に加工され、自分の身体特性まで侮辱され、意味不明な言説で、誹謗中傷してくるといったこともあった。中傷をしてくる人は、それをけむにまいて、その周辺の人を見方に付け、煽ったり、知らんぷりをしたりした。そしていっこうに謝ろうとしない。さらにちゃらけた言動で「拡大解釈だ」などといって、事態を収拾しようとしていた。本当に腹立たしい。
これは、投稿するたび承認を繰り返し、自己から発せられたメッセージが自己に帰属するというソーシャルメディアの特性からすれば、罪悪感や、集団から排除された気分に陥り、もうやっている意味がそれこそ無くなるので、一旦辞めるに至った。
さらに、これがリアルを浸食する。信頼している恩師と飲んだ時も、もっと静かにしろと怒られた。なんで他人に対して色々言うのかと。その時は、それを説得する力も残っておらず、ただただ家に帰っては落ち込むという日々が続いた。「言葉は剣ではない」などと一線のコピーライターから言われたこともあるが、正直、コピーライターの学校にも通っていたし、そんなこと分かっていた。そんなこんなで、一定の信頼を失ってしまい、イメージも低下した。様々な方法でそれらの回復を試みるが、なかなか難しい。
最終的には鬱になり、病院に通ったりもした。まだ正直、体調は良くないが、良くないなりに、頑張ってやっている。
勿論、私自身が完全に正しい言動をしていたかは定かではない。当時のモノの見方や知識に、幼稚な点はたくさんあったと思うし、まだまだ現時点でも知らないことは沢山ある。
ただ、こういったことは、世の中が許さないものだと思っていた。しかしながら、そういった事実が確かにあった。
ただ私は、本来人同士は共生しないと生きられないということを知っている。なので、そういうことを私にしてきた人達も、それぞれのことがあるんだし、あえて名前は出さないことにした。
おそらくまた「過去を振り返るよりも、未来へ向かって前進しろ」といったことや、「なんで今さら」などといったことを言われるかもしれない。けれど、こういうことを明白にしておく必要があった。
さて、これを読んだ人の苛立ちは、どこに向かえばいいのか。それは、こういったことを二度と繰り返してはいけないという社会をつくって行くということに向かうべきなのではないだろうか。そして私自身もそう願っている。
私はまだ駆け出しだけれど、フリーのデザイナーです。なので、コミュニケーション・デザイナーやプランナー、研究者などからすれば文章や理論の腰は弱いかもしれない。けれど、私なりにこういった事態を経験したことを通して見えてきた様々なことがあるので、それを世の中のために活かしてもらうために、以下にそういった事態が起こる悪いパターンや現象を書こうと思う。
まず、こういう場所での言葉は、一人ひとりが抱えている、それぞれの集団に依存してコード化されることが多いんじゃないかということ。つまり、見ている人にとって、その発言がおかしいと思うことでも、その人の集団では、正しいことだったりするということ。だから、一概に「それはぜったいだめ」などとステレオタイプなどでレッテルは張れない。またアカウントの使用のしかたが「オープン」か「クローズ」かでも、違ってくる。
次に、「無意味に罵ること」と、「指摘すること」「批評すること」は、リアルな社会でも、WEB上でも本来違うということ。明確に区分された自明なことであるということ。ただこれは、五感を使ったコミニュケーションで成り立ちやすいことで、WEB上では、表情や身振り手振りなどのボディーランゲージがなかなか出来ないのでこれの区分は成り立ちにくく、「意味」だけが流布しやすい。リアルにはコミニュケーションのクッション材のようなものがあって、それがWEB上の社会にも、戻ってきてくれることを願ってやまない。
さらに、スマートフォンなどのデジタルメディアと人体は切っても切れない関係になっているということ。共同体意識はそれによって各々の思想や場所などによって個人化し、それぞれの場所で、それぞれの公共意識をつくる。リアルとバーチャルが平行世界でコミニュケーションが成り立っているというより、バーチャルなネットの人格がリアルの方に侵入して来ているんじゃないかということ。だから、WEB上で罵られたことは、リアルでも罵られるということ。それが、家の内と外、電車などの公共空間、道端など、どこまででも着いて来て、これまでの「そこにいったらその集団」といった具合ではなく、「いつでも、すべての集団と一緒にいる」となるのではないかということ。
最後に、批判するなら個人のことなどではなく、問題を批判して、それを問題解決に結び付けなければいけないということ。
頑張って、まずは自分を振り返って、自分のことをやらなきゃいけない。
勿論、〇〇はダメ、とばかりも言っていられないので、僕自身、何言われようと未来に向かって頑張らなきゃいけないな、とも思ってる。この間、駅貼りの広告で知って、感動したコピーがあるので、載せておきます。
「未来にタネをまこう」
グランドスラム、世界No.1への道。
僕にはまだ見えない。
だからまだ、夢が見られる。
http://www.jaccs.co.jp/cm_miraini2/index.html
P.S.
今、東京の下町に住んでます。
下町のおっさんやおばはんは、何か嫌なことがあると、
「んなもん、ずっと気にしてたってしょうがないぜ。気にせずやれや。」と勇気づけてくれる。
こういう世の中に、早くもどらんかな。

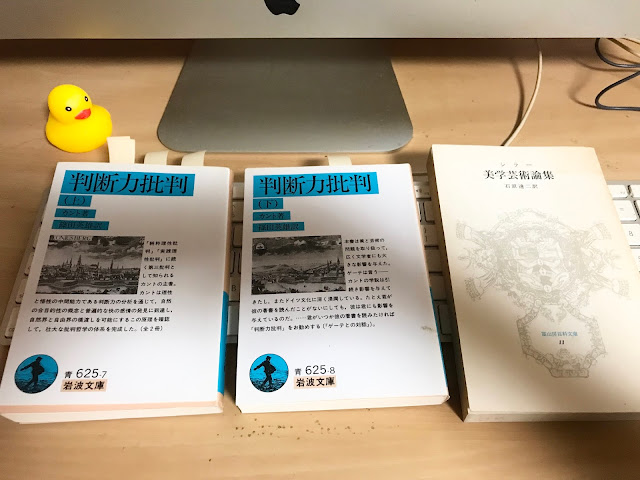
コメント
コメントを投稿